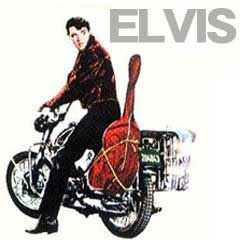50年代〜ケネディ大統領が暗殺されるまでの60年初期のアメリカは、日本人のバイブルだった。その当時のアメリカの雑誌、たとえば「エスクァイア」の広告を観ると分かる。それは類いまれな立派な歴史書という趣だ。
その裏には、なかなか日本人が知らなかったアメリカの悩みがあり、第二次世界大戦後の反動的な右翼の波に押し流されながら、反発して順応を拒んでドロップアウトした若者たちの世界があった、
つまり”ビート”のことだ。ビートジェネレーションは従来の社会の規範かに縛られることなく自由で、根源的な精神を追い求めた。そのルーツはウォルター・ホイットマン (Walter Whitman, 1819年5月31日 – 1892年3月26日)、ハーマン・メルヴィル(Herman Melville、1819年8月1日 - 1891年9月28日)、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(Henry David Thoreau、1817年7月12日 - 1862年5月6日)に辿り着く。
その自由な精神はアメリカ植民以来の超絶主義を継承する。”ビート”の根城はサンフランシスコで、サンフランシスコには、ニューヨークにもロスにもない独特の透明な空気がいまでも漂っている。考え抜いて言葉を選び、行動を選択するより、内面からわき起こる自らの声にエネルギーを注ぐことを大事にした。
言うのは簡単だが難しい。この自らの声にエネルギーを注ぐには、自分を信じる肯定感がしっかりしていることが条件になる。自己効力感も必要だ。そしてそれこそが自由と呼べるものだ。良識と良心がなく、ただ自らの声にエネルギーを注ぐなら蛮行でしかない。そんなものを自由とは言わないのだ。下品なだけの勝手気ままは醜悪だ。
ソローを読んでみたらビートの本質が分かる。それこそがバイブルにすべきアメリカなのだ。
たとえば、iPadという代物、つまりアップル製品が好きなのは、いつのアップルにも、どのアップルにもバイブルにしているアメリカを感じるからだ。でも日本のアップルストアでそれを感じることはない。その理由はアメリカから遠すぎる都市だからだ。自己満足して都市生活を送るより、旅の暮らしの不安のなかに生きる磁気を感じたい。